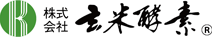特集記事
- 玄米酵素オンラインショップTOP
- 特集記事一覧
- 心身の健康を守ろう!自律神経のバランスを整える栄養と生活習慣
- 心身の健康を守ろう!自律神経のバランスを整える栄養と生活習慣
- 2025年03月14日
「疲れが取れない、イライラする、食事が美味しくない…」そんな日々が続いていませんか?
もしかしたらストレスや生活習慣の影響で、自律神経のバランスが乱れている可能性があります。
自律神経が乱れる原因&体と心のサイン

自律神経は、内臓や血管などの働きを無意識にコントロールする神経系のことで、交感神経(活動・緊張の神経)と副交感神経(リラックスの神経)の2つがあります。
これらは互いにバランスを取りながら、一日を通して身体を最適な状態に保っているため、自律神経のバランスが崩れると、心身にさまざまな不調が現れます。
主な原因には過労、ストレス、生活習慣の乱れによるものが挙げられます。
特に、職場での異動や転勤、引っ越し、育児などの環境変化が影響を与えやすいです。
また、個人差はありますが、更年期に起こるホルモン減少は、自律神経の乱れを起こす原因の一つになります。
現代は「ストレス社会」とも呼ばれ、交感神経が優位になりがち。さらに、ストレスによって飲酒や喫煙、間食が増え、生活習慣病のリスクも高まります。
<身体と心のサイン>
自律神経の乱れにより、以下のようなサインが現れることがあります。
早めにストレスに気づき、対策をとることが大切です。
身体のサイン:疲労感、不眠、めまい、頭痛、動悸、冷え、便秘、過食、味覚障害 など
心のサイン:イライラ、不安感、うつ症状、人付き合いの億劫さ など
自律神経をサポートする栄養素と食材

栄養バランスの偏りは、自律神経の不調を引き起こす恐れもあります。
バランスよく、できるだけ毎日同じ時間帯に食べるようにしましょう。
●食物繊維
腸内環境を整えるのに役立ちます。自律神経と腸内環境は密接な関わりがありますので、意識してとりましょう。
(玄米、野菜、豆類、海藻、きのこ類など)
●たんぱく質
アミノ酸の一つであるトリプトファンは、脳内の神経伝達物質のひとつであるセロトニンの材料になります。
不足すると自律神経の働きが乱れれやすくなるので、毎食適量をとるようにしましょう。
(大豆製品、豆、魚介類 など)
●ビタミンE
血行をよくする作用があり、血行障害による肩こりや冷えの改善に役立ちます。
また、抗酸化作用もあり、活性酸素から体を守ります。
(ナッツ類、玄米 など)
●ビタミンC
神経伝達物質や抗ストレスホルモンの合成に関わっているため、ストレスによって失われやすいビタミンです。
強い抗酸化作用もあります。
(赤ピーマン、ブロッコリー、菜の花 など)
●パントテン酸
抗ストレスビタミンとも呼ばれ、ストレスによる細胞のダメージを和らげるステロイドホルモンの分泌を調整する働きがあります。
あらゆる食材に含まれ、バランスのよい食事を心がけていれば不足することはありません。
(納豆、玄米 など)
●ナイアシン
皮膚や粘膜を健康に保つ、神経の安定に役立つなどの働きがあります。
アミノ酸の一種であるトリプトファンからも体内で合成されます。
(かつおぶし、ピーナッツなどの種実類 など)
●マグネシウム
神経伝達などの多くの生命活動に重要な役割を持ち、筋肉の緊張を緩める作用があり、精神の安定をもたらしてくれます。
(ひじき、ほうれん草、大豆製品、玄米、そば など)
●カルシウム
精神の安定をサポートします。
(小魚、生揚げ、大根葉 など)
自律神経を整えるための生活習慣

生活習慣も自律神経のバランスに大きく影響します。
忙しいと何かとおろそかになりがちですが、日々の積み重ねが、健やかな毎日につながります。
●規則正しい生活リズムを心がける
起床時間、食事時間、就寝時間を一定にすることで、体内リズムを整えましょう。
●リラックス習慣を取り入れる
【深呼吸】不安や緊張を感じたら、腹式呼吸を意識しましょう。
- 3秒間ほど頭の中で数えながら、ゆっくり口から息を吐き出す(お腹がへこむのを意識)。
- 同様に、ゆっくりと鼻から息を吸い込む(お腹が膨らむのを意識)。
- これを5〜10分繰り返す。※お腹の動きを意識することで、より深い呼吸ができます。
【入浴や音楽】温かいお茶を飲むのもオススメ。
【適度な運動】軽い散歩やストレッチで、気分をリフレッシュ。
●質の良い睡眠をとる
夜更かしや朝寝坊は、自律神経に悪影響を与えます。
眠る前は、交感神経の緊張を緩め、副交感神経を優位にするために、リラックス時間を確保しましょう。
また、睡眠ホルモンのメラトニンは、幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンからつくられます。
セロトニンの原料となるトリプトファンを多く含む食べ物(大豆製品、緑黄色野菜 など)や、合成に欠かせないビタミンB6をとるようにしましょう。
***
ストレス社会の現代において、自律神経を整えることは心身の健康を維持するために不可欠です。
バランスの良い食事、規則正しい生活、リラックス習慣を取り入れ、ストレスとうまく付き合いましょう。
【参考文献】
『よくわかる生理学の基本としくみ』(秀和システム)
『改訂新版 いちばん詳しくて、わかりやすい! 栄養の教科書』(新星出版社)
『正しい知識で健康をつくる あたらしい栄養学』(高橋書店)
こころもメンテしよう(厚生労働省)
【関連記事】
気持ちを立て直したい時に食べたい食材と、自律神経のバランスを保つコツ
マインドフルネスで脳をリフォーム
血液検査で「ストレスの度合い」を見る方法
日本人の遺伝子に合ったストレス対処法 日々できるセルフケア 5つのポイント
梅雨時期に多い「天気痛」とは?